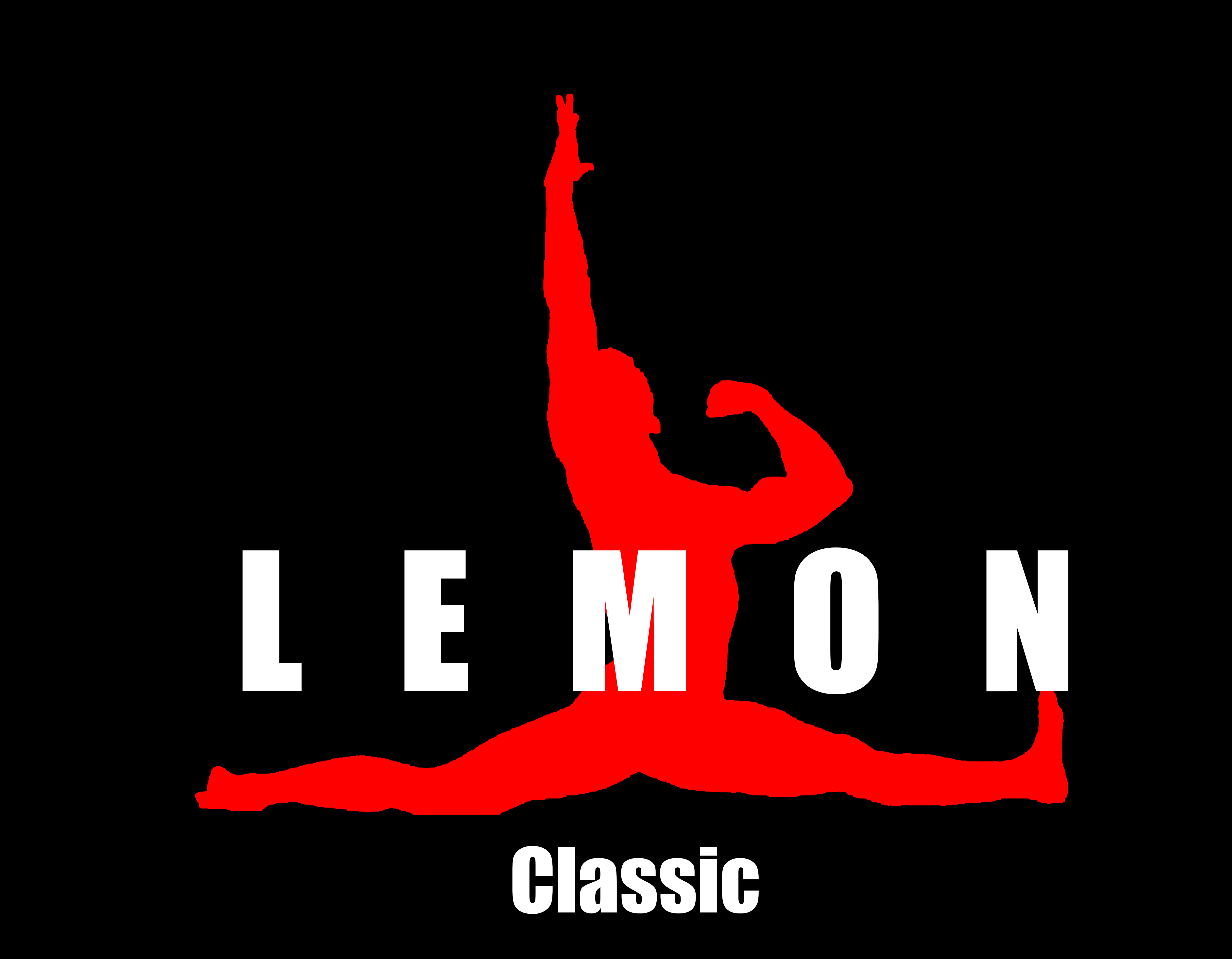こんにちは、博水5代目です。
先日、福岡市立三宅小学校の5年生を対象に、「福岡のギョロッケを加工している人に直接聞いてみよう」という授業に登壇しました。
子どもたちが食べている給食の“福岡のギョロッケ”を通して、地元の魚を食べる意味、仕事の魅力、そして地域を支える人の想いを伝える時間となりました。
「給食でギョロッケを食べる理由」から始まった授業
今回の授業は、水産業の課題を社会科で学んだ子どもたちに、給食で食べる水産物のひとつ「福岡のギョロッケ」をなぜ食べるのか?どういう想いで作られているのか?をお話しました。
「地元でとれた魚を、地元の会社が加工して、地元の学校で食べる」――そのつながりを感じてもらい、子どもたち自身の将来を考えるきっかけとなることが目的です。
福岡のギョロッケは、今まで捨てていたブリのアラや骨の部分をレトルト加工し、柔らかく仕上げてすり身と合わせて作ったもの。
地元の水産会社さんが扱う福岡市産のブリを使い、博水が地元で製造しています。

私は授業の中で、こう伝えました。
「僕たちがいないと、このブリギョロッケは食べられません。
でも僕たちだけじゃ作れない。漁師さん、給食の先生、市の職員さん、たくさんの人が関わっているんです。」
「だから、みんなが食べる“てんぷら”の一つひとつにも、誰かの想いが込められています。」
“作っている人”の想いを伝える
授業では、魚を無駄にしないために生まれた「練り物の知恵」や、普段は捨てられてしまう魚「えそ」を活用していることを紹介しました。
えそは小骨が多く、そのままでは食べづらい魚ですが、すり身にすることでおいしく食べられます。
子どもたちは「えそって初めて聞いた!」「そんな魚も食べられるんだ!」と興味津々でした。
給食で子どもたちが食べる“福岡のギョロッケ”も、魚を無駄にせず大切に使いたいという想いで作られていることを伝えました。
また、食品ロスを減らす工夫や、後継者不足という現実にも触れました。
「水産加工を続けるのは簡単じゃない。でも、地域の魚を生かすために、僕たちは挑戦を続けています。」
という言葉に、子どもたちは真剣な表情で耳を傾けてくれました。

広がる“学びの輪”
授業後、嬉しいことがありました。
授業を受けた子どもたちがお母さんと一緒に博水のお店に来てくれたんです。
「学校でギョロッケの話を聞いたよ!」「これが“てんぷら”なんだよ!」と話しながら、商品を選ぶ姿に胸が熱くなりました。
教室での学びが家庭の食卓につながり、地域の食文化を“自分ごと”として感じてもらえたことが何より嬉しかったです。
先生方からの感想
「給食を食べながら“これがてんぷらか!”と子どもたちが口々に話していました。授業前は“てんぷらって何?”という子も多かったので、認識が変わったことが嬉しいです。」
「どのクラスもとても楽しく学べ、貴重な機会になったと教頭先生からもお言葉をいただきました。」
「主幹教諭の先生からは“毎年実施してもいいなと思う、よく練られた授業でした”との感想をいただきました。」
練り物の文化を未来へつなぐために
練り物文化を未来へ残していくためには、子どもたちに練り物のことを知ってもらうこと、そして美味しい練り物を実際に食べてもらうこと、さらに商品だけでなく「作る人」の想いを知ってもらうことが大切だと思っています。
その想いから、博水では学校給食の製造や地域イベントへの出店など、さまざまな活動を続けています。
今回は「授業」という形で、子どもたちに直接、練り物のこと、伝統を受け継ぐ意味、そして給食を作る人の想いを伝える貴重な機会をいただきました。
真剣な表情で聞いてくれた子どもたちは、授業後にたくさん質問をしてくれて、「ギョロッケを食べるのが楽しみ!」と笑顔で話してくれました。
子どもたちにとって少しでも学びや気づきになっていたら嬉しいです。
そして私たちも、こうした活動を通して、練り物の可能性を広げ、食の未来をつないでいきたいと思います。
関連リンク

“食べる”の向こうにある人の想いを、子どもたちと一緒に感じました。